Q&A
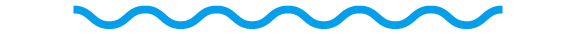
浪江町への移住・定住について、よくある質問をまとめました。
以下Q&Aで解決できない場合、もしくは知りたい項目がない場合はお問い合わせよりお気軽にお問合せください。
- 浪江町の人口と居住者数はどれくらいですか?
- 浪江町の人口は14,917人(男性7,420人、女性7,527人)で、世帯数は6,645世帯です。そのうち、町内居住人口は増加しており、令和6年4月末時点で2,227人、1,395世帯です。
- 浪江町内の空間線量はどれくらいですか?
- 町内の中心部の空間線量は毎時0.05~0.34マイクロシーベルトです。
平常時では、年間1ミリシーベルトが基準値として用いられています。ここから毎時に直すと、0.23マイクロシーベルト毎時が基準値とされています。
しかし、この基準値を超えたから危険とか、超えなければ安全であるといった、安全と危険の境界を示すものではありません。さらに、この基準は平常時の基準であり、事故後の回復や復旧の時期等においては、線量限度は年間1~20ミリシーベルトの間とされていますので、町内の多くの地点は生活するには問題ない値となっております。
- 町内の事業者数はどれくらいですか?
- 現在約200の事業者が町内で活動しています。
- 買い物環境はどうなっていますか?
- 町内で食料品や一般生活雑貨の買い物ができるのはイオン浪江店、道の駅なみえ、まち・なみ・まるしぇやコンビニエンスストア(4か所)などがあります。日々の生活に困ることはありませんが、町内だけで生活に必要とされるすべてを調達することは難しいのが現状です。家具家電などの大きなお買い物は、近隣の南相馬市(車で30分程度)にお店がたくさんあるので不自由を感じることは少ないと思います。
- 交通事情はどのようになっていますか?
- 浪江町には国道6号線、114号線、常磐自動車道、JR常磐線など主要幹線があり町内外からのアクセスは良好です。町の中心部から高速道路のインターまでは車で10分以内です。
JR常磐線は在来線が1時間に1本程度の運行。特急は上下3本が停車し、東京には約3時間、仙台には約1時間余りで行くことが可能です。
路線バスは、新常磐交通株式会社 富岡駅~大野駅~浪江(FH2R)線が平日のみ運行、東北アクセス株式会社 双葉・浪江~南相馬線が平日および土曜日に運行しています。
また町内の交通手段はレンタカーとタクシー、カーシェアがあり、オンデマンド配車サービス"スマートモビリティ"の実証が行われています。
- 住宅事情はどうなっていますか?
- 空き家・空き地バンクの登録状況については、空き地に比べ、空き家の登録は多くありません。町には移住者の方も入居可能な町営住宅がありますが、空室があまり出ないため、入居は抽選となる場合があります。
民間の賃貸住宅や売り家については、相談窓口担当が不動産会社への相談同行も可能ですので、ご希望の際はご連絡ください。
- 医療機関はありますか?
- 町内には診療所が1か所、歯科医が2か所あります。
令和5年10月から震災後初となる調剤薬局が新たにオープンしました。
また、車で30分程度の南相馬市には大きな市立病院があります
- 小中学校はありますか?
- なみえ創成小学校、なみえ創成中学校があります。同敷地内には浪江にじいろこども園があります。
- 高等学校はありますか?
- 震災後には町内に高校がないため、町外の高校へ通うことになります。近隣では南相馬市に「原町高等学校」「相馬農業高等学校」「小高産業技術高等学校」が、広野町に「ふたば未来学園高等学校」があります。電車で通うことができ、通学費については町の助成制度があります。
- 今後の浪江町の整備計画を教えてください。
- 新たに浪江駅西側に介護関連施設、地域の交流施設、図書館、子どもの屋内あそび場、屋外運動場を備えた『ふれあいセンターなみえ』が完成しました。
また、駅東側では、浪江駅周辺グランドデザイン計画に基づく施設整備を進めており、交流施設、商業施設、公営住宅、交通広場、芝生広場等が整備され、町のにぎわいの中心的な場所となる予定です。
- 現在の浪江町内の主な産業を教えてください。
- 現在4つの産業団地を整備しており、製造業などの企業が立地しております。また、建設業のほか、震災前からの産業である農業、漁業が再開しています。農業では玉ねぎ、エゴマ、トルコギキョウ(東京オリンピックのメダリストに贈るブーケに採用)、ストック、カラーなどの野菜類や花の栽培、水稲栽培が主に行われています。漁業ではシラス、カレイ、ヒラメなどの水揚げが多くあります。
- 仕事はすぐに見つかりますか?
- 業種にもよりますが、町内の多くの事業所が人員不足となっており、ハローワークの求人情報にもかなりの数の募集が出ています。工業団地に新しくできた企業もあり、最先端技術の企業で働くことも可能です。
- 移住して一番困ることは何ですか?
- 買い物場所と医療機関が都市に比べて十分ではないことです。ほとんどの方は町内施設と合わせてお隣の南相馬市にあるお店や医療機関を利用しています。
- 町ではどんな過ごし方ができますか?
- 道の駅なみえでは、地酒や野菜、海産物などの地場産品の購入ができるほか、同敷地内にはポケモンの遊具で遊べるラッキー公園があり、お子さんも楽しむことができます。
町内には和・洋・中ほか様々な飲食店があるので、お店巡りも楽しいです。
中心部から少し行くだけで豊かな自然を感じられるのも町の魅力の一つ。広い空の下、季節ごとに変わる景色の中を散歩するのも気持ちがいいです。
娯楽施設は少ないですが、浪江町の本当の楽しみはハードではなく"人"です。町内にはゼロからイチを作り出そうとしている面白くて元気な方がたくさんいらっしゃいます。イベントも多く開催され、多くの移住された方も主体的に参加されています。
- 浪江町に進出した企業はありますか?
- 町内には産業団地が4か所あり、福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)、福島高度集成材製造センター(FLAM=ウッドコア)、脱炭素化を見据えて米などを原料とするプラスチックの製造を行うバイオマスレジン福島など、様々な業種の企業が進出しています。
また、福島をはじめ東北の復興を実現する夢や希望となるとともに、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指して、多様な研究開発、産業化、人材育成に取り組み、福島イノベーション・コースト構想を更に発展させる司令塔としての役割も果たすよう、復興庁が中心となって設立した新たな法人、福島国際研究教育機構(略称:F-REI「エフレイ」)が浪江町に設立されました。